「初めにことばがあった」柳父章
確かに「初めに言葉ありき」ってのはピンと来なかったんですよね、わたしは。「ロゴス」=「言葉」でいいの?って。だけどなるほどキリスト教の宣教と翻訳というのは、他宗教と比べると異質なのですね。これが一つの真相かどうかはともかく、面白い指摘ではあります。
「明治に生まれた翻訳ことば」飛田良文
「演説」は福沢諭吉が作った翻訳語だ、というのは嘘。なのだそうです。当時の翻訳語のなかには、英華字典(英語-中国語辞書)から採られたものが数多く存在するのだけれど、現代日本語と古語と中国語と各種西洋語にまたがることだから、これまではなかなか研究されてこなかったのだとか。
「シェイクスピア翻訳史の端緒と現在」河合祥一郎
今はポップ・ミュージックの影響で、昔と比べれば日本語にも脚韻の存在感が増してきていると思うので、そういう訳も有りだと思います。でも日本語で韻を踏むと、重くなっちゃうんだよね。何にしろ、普通は犠牲にしてしまうところにまで気を配った翻訳が(多分これからも続々と)現われるのは、シェイクスピアならではでしょう。翻訳の可能性を極限まで追求してほしい。
「雨森芳洲と翻訳」大西比佐代
江戸時代の通訳・翻訳者である雨森芳洲に見る、通訳・翻訳の真髄。現代のやり方が必ずしも正しいとは限らないけれど、それにしても当時としては際立った精神の持ち主だったようです。
「カフカ以前とカフカ」池内紀
最後にセリフの改行について触れられています。丘沢静也に対する回答のように感じてしまうのは、ワイドショーじみた下世話根性かな。
「「バラク・オバマ」を翻訳する」荒このみ
比喩的な意味での「翻訳」かというとそうでもない。というのは、イギリス英語とアメリカ英語の違い、黒人英語と白人英語の違い、黒人英語の日本語訳、などを踏まえて、白人英語を話していたオバマがアフリカン・アメリカン票を獲得するために黒人英語を話し出すという展開にまで広がると、なるほど言葉かと納得です。
「同時翻訳の難しさ」松本道弘
何だこりゃ? 元通訳らしいのだが、翻訳者に対するルサンチマンが文章のそこかしこから滲み出ていて見苦しい。悪文を貶す割には稚拙な日本語だし。「耳触りがいい」を「耳障りがいい」と書くのは単純ミスにしても、「ケータイ小説ライターが、ベストセラー10人のうち5人までが、占めていたという事実をTIME誌で知って、思わず赤面した」になると逆にオモロイ。文法的にどうこうは勿論、なぜそこで赤面するのかがわからん。ところどころでいいことは言っているのにね。
「自動翻訳機はどこまで進むのか」富士秀
インターネットの出現により、自動翻訳機の使い方に新しい発想が生まれた、とか、実は翻訳スピードというに限ればどんな優れた翻訳者にも適わないのだ、とか、言われてみればその通り。なるほどそういう方向ではすでに「実用」化されているといってもいいのかな。
「抒情の罠――金素雲と金時鐘」
これは翻訳や言葉の問題というよりも、テクストをテクストとして読めない一部の研究者の問題なんじゃないのかなあ。
「ペソアを翻訳する――『不安の書』と相まみえて」高橋都彦
フェルナンド・ペソア『不安の書』の邦訳について。――というより、ペソアと『不安の書』そのものについてのエッセイのような感じ。
「誤訳の名作――アメリカ文学作品邦題再検証」舌津智之
その名の通りの内容なのですが、なかでも、一見するとオリジナルな意訳に見える『若草物語』についての指摘が鋭い。
「翻訳という名のアート」江藤裕之
はからずも(?)いずれも詩についての文章でした。
「短歌の翻訳」宿谷睦夫
押韻と定型の両面から短歌・英詩について概説したあとで、実際の短歌が紹介されているのですが……できればもっと人口に膾炙した作品を例に出してほしかった。
--------------
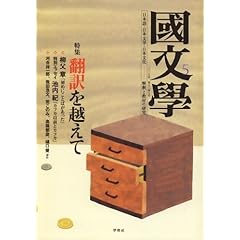 『國文學』2008年5月号
『國文學』2008年5月号
 amazon.co.jp で詳細を見る。
amazon.co.jp で詳細を見る。