『Ô Dingos, Ô Châteaux!』Jean-Patrick Manchette,1972年。
おかしな邦題は、ランボーのもじりらしい原題を、中也訳ランボーでもじったものとのこと。〈古典新訳文庫〉というブランドが確立されているからこそ採用できたんでしょうね、単発でこの邦題は勇気がいるものなあ。
暴力とセックスが日々エスカレートしているのが世の習いゆえ、今これを読んで暴力描写に衝撃を受ける!ということはありません。血なまぐさいのが苦手な人もそこはご安心を。
とはいえ衝撃的ではあります。乾いた文体で綴られる、刹那的でクールで子どもっぽいキチガイたち。みんなただただ好き勝手に突っ走る疾走感。
感心したのはペテールの存在で、「嫌なガキ」がある種「相棒」になる過程がすごく自然に描かれていることです。誘拐・逃亡・戦いというのは「取りあえずの結びつき」にはうってつけだったにしろ。
しかも変な人たちの「変」さがぶれていません。最初は嫌なガキだったのに最後はいい子になってたとかじゃありません。最初から最後までこまっしゃくれたガキであることに変わりはありません。
ジュリーは最初っから最後まで熱っぽい。熱でぼうっとしているときに、意識ははっきりしているのに、ふと気づいたらあれ?何やってんだ?みたいな危うさを常に持っている女の子です。微熱どころか高熱状態で突っ走るので、何をやらかすんだかわかったもんじゃありません。誘拐犯と殺し屋がいるから、かろうじて「追われるヒロイン」でないこともないけど、完全にサイコ女の一人上手な狂宴でした。いや、でも意外と逃亡映画のヒーロー/ヒロインってみんなこんな感じのような気も。。。
殺し屋は精神的に何か抱えているんですが、そんな内面のうじうじなんか書かないわけです。ぜったい病んでるんだけど、描かれるのは吐き気とかの肉体的な描写だけ。そうすると、どこか壊れているんだけどそれが個性になっちゃうんですよね。帽子をかぶっているとか足を引きずっているとかみたいに。
解説でマンシェットの映画の話に触れられていましたが、本書のクライマックスである「城寨」での戦闘シーンを映画化したら面白いだろうなあ、と思います。鏡の館(?)の銃撃シーンって何の映画でしたっけ?忘れてしまいましたが、本書の巨人の部屋とか寄せ集めの建物とか迷路みたいな空間をいっぱいに使った銃撃シーンをぜひ見てみたいものです。
精神を病み入院していたジュリーは、企業家アルトグに雇われ、彼の甥であるペテールの世話係となる。しかし凶悪な4人組のギャングにペテールともども誘拐されてしまう。ふたりはギャングのアジトから命からがら脱出。殺人と破壊の限りを尽くす、逃亡と追跡劇が始まる!(カバー裏あらすじより)
-----------
 『愚者が出てくる、城寨が見える』
『愚者が出てくる、城寨が見える』
 オンライン書店bk1で詳細を見る。
オンライン書店bk1で詳細を見る。![]()
 amazon.co.jp で詳細を見る。
amazon.co.jp で詳細を見る。
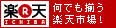 楽天市場で詳細を見る。
楽天市場で詳細を見る。![]()