欧米の漫画事情が紹介されています。リル・アブナーという漫画に出て来るシュムーという動物が、まんま手塚キャラみたいでおもしろい。アダムス・ファミリーが「幽霊一家」というタイトルで紹介されていたり、「タンタンの冒険」が「チンチンの冒険」と紹介されていたりという時代も感じさせます。
「雷鳴と陽のもとに」チャド・オリヴァー/矢野徹訳(Between the Thunder and the Sun,Chad Oliver,1957)★★★★☆
――アルデバラン第四惑星の人類はいま絶滅の危機にある。だが、宇宙法を冒してまで、彼らを救う必要があるのか?(袖コピーより)
過去の植民・征服の歴史から学んだ結果、宇宙で知的生命体を発見してもそれが未開状態の人類であるのなら「手をふれるな!」が法律で定められていたり、往復十年に及ぶ宇宙旅行にともなう性欲問題に触れられていたりと、現実的な手続きを踏んでいることに感心しました。ことは法律的問題と道徳的問題どちらを取るかという問題だけではなく、政治的問題をも考慮しなくてはならなかったのだという結末もよくできています。それだけに惜しいのが、人類を救うだけではなくいわゆる「文明」を授けるのは行きすぎで、ちょっと話のピントが見えにくくなってしまっています。
「夢は予言する 世界ファンタスティック通信」
ジャワ付近のプララーペという小島が噴火沈没する夢を見た新聞記者が、その夢をメモしておいたところ、記事だと勘違いされて新聞に載せられてしまった。当然記者は大目玉を食らったが、その後、実際にプララーペ島が噴火沈没したという外電が飛び込んできた……という「実話」コラムが載っています。1883年の話です……。
「罪なき罰」レイ・ブラッドベリ/小笠原豊樹訳(Punishment Without Crime,Ray Bradbury,1950)★★★☆☆
――愛する妻に裏切られた男の採るみちはただ一つ。非合法とは知りながら犯した感情浄化殺人の罰は……(袖コピーより)
ロボット殺しは罪か否かという古典的な(まあ時代的には古典で当然なんですが)命題に、仮装殺人会社というアイデアをからめた話なのですが、最後はブラッドベリらしいべたべたな愛情物語になっています。
「ロボット還る」ロバート・ムーア・ウィリアムズ/大山優訳(Robot's Return,Robert Moore Williams,1938)★★★☆☆
――一枚の古い星図をたよりに、その小さなロボット達は遙かな星からやって来た――祖先を、ふるさとを求めて……(袖コピーより)
これまた安心して楽しめる古典作品。ロボットたちが(それと知らずに)自分たちを作った人類滅亡後の地球を訪れる内容です。三体のロボットたちがそれぞれ懐疑的だったり・自尊心が高かったり・現実を受け入れるタイプだったりと、おのおの真実を知ってしまうことに対する心理状態が三者三様で読ませます。
「失われた大陸を求めて(サイエンス・ノンフィクション2)」斎藤守弘
タイトル通り、失われた大陸、すなわちムー、アトランティス、レムリア等々についての概説です。否定的でも肯定的でもなく、紹介といった感じの文章でした。
「地上にいっぱい太陽を」アイザック・アシモフ/草下英明訳(Heaven on Earth,Isaac Asimov)
アシモフの科学エッセイ。12進法、60進法の話から、ぐるり360°の話となり、最後は天体の話になっています。いや〜話し上手ですね。算数の話かと思ってたら、科学の話になってるんですから。
「ごきげん目盛」アルフレッド・ベスター/井上一夫訳(Fonoly Fahrenheit,Alfred Bester,1954)
――パラゴン第三惑星の稲田に影絵のような男たちの行列。殺されてむごたらしく捨てられた、八つの子供の死体を探す、怒りの、悲しみの群……(袖コピーより)
これは『影がゆく』『願い星、叶い星』で中村融訳を読んだので、今回はパスします。
「地球物語24 地球の生成から消滅まで」日下実男
1961年から行われていたソ連の核実験の話と、人類は進歩するかという話です。技術的にはケタ違いだろうけれど、からだの方はむずかしい、けどサイボーグなら、という話。
「さいえんす・とぴっくす」
イギリスに「垂直離陸式ジェット機登場」や、自家用「ヘリポッド」のセールスなど。
「愛の宿り」多岐川恭 ★★★☆☆
――駅のベンチにひっそり転がる汚い石ころが、平凡な男女の心を結びつけたのだが……ミステリイ界の異才が描くロマンチック・ファンタジイ!(そで惹句より)
多岐川恭というと男と女の話というイメージがあるのだけれど、期待を裏切らない作品です。真実の愛情を皮肉るのにSF小道具を使うあたりがうまいですね。「男と女」作家がSFを書く必然性がちゃんとあるわけですから。
「白昼の襲撃」星新一 ★★★★☆
――二十世紀のアリゾナに、拳銃腰にカウボーイ・ハット、馬上ゆたかな西部の男が現れた! SFショートの名手が放つSF西部劇!!(袖コピーより)
何でも撃ちまくるガンマンに、アパッチ族の襲来と、ウェスタン的な見せどころもたっぷりの作品です。「少しばかりおそすぎた」のセリフがおしゃれです。
「スペース・ファンサイクロペディア5 続・太陽系アウトロウ」草下英明
ボーデの法則なんてどこ吹く風の小惑星群や、逆時計回りをする木星の衛星などなど、「アウトロウ」な星たちの紹介です。
「全船退避せよ!」ウィリアム・T・パワーズ/宇野輝雄訳(Meteor,William T. Powers,1950)★★★☆☆
――色めきたった宇宙塵部から、ただちに非常警報が飛んだ。大隕石接近! 大隕石接近! 地球・火星間航路の全船舶は緊急退避せよ!(袖コピーより)
ちょびっとだけ人間ドラマがあるほかは、ただいたずらに大騒ぎが描かれている(というか描かれていないというべきか)ようで、ちょっと盛り上がりや緊迫感に欠けます。
「別人になった娘 世界ファンタスティック通信」
これまた胡散臭い話を……(^_^;。ハンガリーの15歳の少女が、突然スペイン語を話し出し、自分は45歳の子持ちのスペイン人だと言い出した――という、定番の話です。
「サイエンス・スクリーン」
ヴェルヌ『神秘の島』と、怪獣映画『コンガ』について。
「災厄のとき」アイザック・アシモフ/神谷芙佐訳(The Evitable Conflict,Isaac Asimov,1950)★★★☆☆
――世界の計画経済を司る万能の電子頭脳が、突然、原因不明の経済事故を惹き起した――次に来るものは世界恐慌と……そして戦争か?(袖コピーより)
『われはロボット』の一篇でもある、ロボット三原則を扱った古典的名作です。電子頭脳は間違ったりしない、ではデータが間違っているのでは? データも間違っていない、では……という謎解き小説にも似た考え方にまず惹かれます。
「プロクシマ目指して」ウラジーミル・サフチェンコ/袋一平訳(Вторая экспедиция на Странную планету,Владимир Савченко,1960)★★★☆☆
――快速で自転する怪惑星上に、無数のミサイル群を乱舞させる知的生命の正体は? 現代ソ連SF界の新鋭が、壮大なスケールで暗黒の宇宙に描く力作!(袖コピーより)
前半は謎の惑星探査、後半は逃げたり戦ったり希望を持ったり忙しい。高速で自転しているため傾かなければ立っていられない惑星、ミサイルや通信は届くのに姿の見えない生命体、探査当時はあった大気が惑星から消えてしまった謎……そして姿を見せた生命体の正体……前半は非常に面白い内容でした。後半になると、乗員の意見が分かれたりといった人間ドラマがあったり、描かれている撃墜の方法が難しすぎてよくわからなかったり、それまでのことは何だったのかと思うくらい楽天的な結末だったり、何だかピントのはっきりしない作品でした。
-----------------
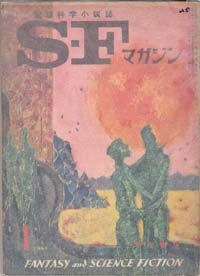 『SFマガジン』1962年1月号
『SFマガジン』1962年1月号