『赤い右手』ジョエル・タウンズリー・ロジャーズ/夏来健次訳(創元推理文庫)
『The Red Right Hand』Joel Townsley Rogers,1945年。
喜国雅彦『本格力』で好評価だったので再読しましたが、やはりわたしにはまったく面白く感じられませんでした。
謎のうちで重要な一つを挙げるとすれば、まんまと行方を晦ました醜い小男の消息だ。茶色の髪を振り乱し、赤い目をぎらつかせ、耳は裂け、犬のように尖った派を持ち、脚は栓抜き《コークスクリュー》並みに捻じくれ、身の丈は切りつめたかのように低い男が、セントエーメを殺害したのち、いかにしてこの片田舎から姿を消したか、それが最大の問題だ。第二はこの小男がセントエーメの右手をどこへやったのかだ。遺体からは右手だけがなくなっていた。謎はそればかりではない。小男がクラクションを鳴らしつつ、三叉路で立ち往生していた私の車の脇をいかにして通り過ぎたのかという疑問だ。私が車を目撃しなかったのは間違いない。
冒頭の文章はすこぶる魅力的です。人間離れした犯人の姿も荒唐無稽が半分、雰囲気作りが半分といったところでしょうか。ところがこんな魅力的な冒頭から、語り手の医師がではこれから謎を解こうとするのかというとそんなことはなく、これまでに起こった山ほどの殺人事件が時系列を無視してひたすら語られてゆくだけで捜査も推理もないまま200ページほど費やされてしまいました。
そしてどう考えてもこの語り手のリドル医師が犯人の叙述トリックだとしか思えません【※ネタバレ*1】。ここまであからさまだと、実際に犯人であろうとなかろうと真相がわかった途端がっかりするに決まっています。
ただ、なぜか読ませるんですよね。探偵役の医師が行く先々で人が殺されてゆくというのは金田一耕助ぽくもありますが、その医師がやたら饒舌で、冒頭みたいな装飾過多な文章で事件が次々起こるのは、パルプ作家の面目躍如といったところでしょう。
何もしないまま200ページを過ぎたころ、今度は唐突に推理が始まります。ただの妄想かと思ったらちゃんとした推理だったんですね。そこにびっくりです。一人何役もの入れ替わりトリックと、右手が消えた理由【※ネタバレ*2】も明らかになり、それなりに(むしろ過剰なまでに)本格の体裁は整っていました。ただ、本格ミステリの常として、犯人なんて誰でもいいです――というくらい、誰が実は誰で実は誰だったという面倒臭い話でした。
国書刊行会版の刊行当時の評判は日本のマニアが喜んでいただけだと思っていたのですが、むしろ原書の出版直後からアメリカ国内外で話題になっていたと解説に書かれていて驚きました。フランスで賞を受賞したということは本格ミステリとして評価されたわけではないのでしょう。さすがに信頼できない語り手による実験的な作品だと思われたわけではないでしょうし、ノリのいい犯罪小説といった評価だったのでしょうか。実際、読んでいる最中は「オッターモール氏の手」と「放心家組合」を混ぜたような話かと感じていましたし。
エリナ・ダリーは縁あって裕福な実業家イニス・セントエーメと婚約し、車を駆ってハネムーンに出発した。ところが希望に溢れた旅路は、死んだ猫を抱えたヒッチハイカーとの遭遇を境に変容を余儀なくされる。幸福の青写真は引き裂かれ、婚約者と車を失ったエリナは命からがら逃げ惑う破目に。彼女を救ったリドル医師は、悪夢の一夜に起こった連続殺人の真相に迫ろうとするが……。(カバーあらすじ)
[amazon で見る]
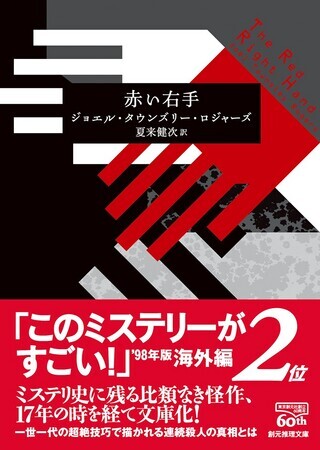
*1 実は違うものの。
*2 右手に特徴のある人物の死体を別の人物のものに錯誤させた。