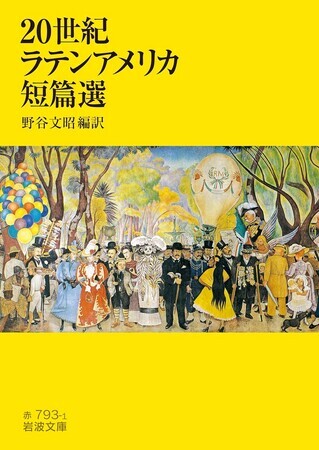一番新しい作品で1991年、古いものだと今から百年以上前の1912年の作品が収録されています。テーマごとに四つの部に分けられていますが、各テーマの範囲が広すぎてテーマ別に分ける必要性が感じられません。
「I 多民族・多人種的状況/被征服・植民地の記憶」
「青い花束」オクタビオ・パス(El ramo azul,Octavio Paz,1949)★★★★☆
――僕は服を着て、靴をはいた。宿の入口で片目の主人に出くわした。「どこへ行くのかね」「散歩だよ。ひどく暑いね」「だが店は閉まっとるよ。それにここは道に明かりがない。部屋にいる方がましだと思うが」、僕は肩をすくめ、闇の世界に足を踏み入れた。ゆっくりと長いこと歩いた。身構える間もなく、背中にナイフのきっ先が当たり、やさしい声がした。「あんたの目をもらうだけだよ」「何でもやる。殺さないでくれ」「殺すつもりはないよ。恋人の気まぐれでね。青い目の花束が欲しいと言うんだ」
メキシコ出身。集英社文庫『ラテンアメリカ五人集』で既読のはずですが忘れていました。タイトルがタイトルなだけに、「赤レンガの床」「灰色がかった蛾」「黄色い光」「緑色に塗られた階段」「白い塀」といった色の描写に目が行きます。「宇宙とは巨大な信号のシステムであり(中略)星のまたたきは、この会話の中にちりばめられた休止と音符にほかならなかった」「夜は瞳の園」という星を目になぞらえた表現も、内容からすると象徴的です。結局のところ語り手の身に起こったことはよくわかりません。語り手の目は実際に青くなかったのか。それともまつげが燃えるほど火を近づけられて焼けて青くなくなってしまった。すでに目がなかった……? 宿の主人が片目だったことを鑑みると、宿から出てきた語り手を宿の主人と間違えて襲ったと考えるのが妥当でしょうか。「青い目をした者なんてほとんどいないもんだから」、もう片方の目も奪うつもりで。
解説によると、「先住民文化を背負った若者とヨーロッパ的教養の持ち主で外見も異なる語り手の出会いがもたらす小さなドラマ」と書かれてあり、青い目にはそういう意味があるのかと目から鱗が落ちました。日本人から見るとどちらも外国人だものなあ。
「チャック・モール」カルロス・フエンテス(Chac Mool,Carlos Fuentes,1954)★★★☆☆
――ついこのあいだ、アカプルコでフィリベルトが溺死した。書類カバンを開けてみると、ちゃちなノートが入っていた。〈おれが前から捜していたチャック・モールの複製があると、ペペが教えてくれた。〉〈買値より送料の方が高くついてしまった。〉〈朝、目を覚ますと配水管がおかしくなり、地下室が水浸しになっていた。〉〈ぞっとするような悲鳴で一時に目が覚めた。〉〈地下室は乾いたが、チャック・モールは苔むしてしまった。なんだか像もやわらかくなっている。石像ではなく石膏製だったのだ。〉〈チャック・モールの腕に毛が生えている。〉
パナマ出身。ごくオーソドックスな人形の怪――というのはフィリベルトの妄想の産物で――と思われたものが実は――というところまで、怪談として読めば極めてオーソドックスな作品です。
「ワリマイ」イサベル・アジェンデ(Walimai,Isabel Allende,1989)★★★★☆
――わしの名はワリマイで、わしらの言葉では風を意味する。その話をしてやってもいい。あんたはもう実の娘同然だからな。あるときピューマの足跡を追ったわしは、えらく遠出してしまい、兵隊たちに捕まってしまった。お天道様が昇ってから沈むまで、ゴム採集で働かされた。ゴムの仕事を二週間続けると、監督は紙きれをくれ、囲われている女のところへ行けと言った。娘はイラ族の出だった。娘の魂はすっかり弱っていた。
ペルー出身。短篇集『エバ・ルーナのお話』からの一篇。軍部に使役される先住民という社会問題が、いつしか死者の魂と共生する話に移り変わっている、まさに南米マジックリアリズムといった作品です。その一方でマジックではないただのリアリズムだと思って読むならば、妄想によって人を殺すサイコパスの話でしかないわけで、地域は変われどアフリカの一部には今もウィッチドクターがいることを考えると、文化の違いがそれだけでファンタジーになることもありそうだとさえ思ってしまいました。
「大帽子男の伝説」ミゲル・アンヘル・アストゥリアス(Leyenda del Sombrerón,Miguel Ángel Asturias,1930)★★☆☆☆
――修道士は穏やかな日々を過ごしていた。そんなある日、修道院の塀に沿った道を、男の子が一人、ゴムまりをつきながら通りかかった。するとそのまりが僧房の窓から中に飛び込んでしまった。やがてこの信心深い男の胸に、まりみたいにぴょんぴょん跳ねてみたいという狂気にも似た思いが生まれてきた。寺院の入口で信者たちを待ちながらも、修道士は想像の中でまりと戯れていた。あの軽さ、すばしこさ、白さときたら……だが、もしもあれが悪魔だとしたら……。
グアテマラ出身。わけがわかりませんでしたが、大帽子男(ソンブレロン)とはグアテマラに伝わる妖怪の伝承なのだそうです。だからといって白い鞠が黒い大帽子になる道理もないわけですが、シュルレアリスムに影響を受けたと解説に書かれてあってさもありなん。マジックリアリズムという用語の生みの親だそうですが、わたしの知っているマジックリアリズムとは違いました。悪魔に憑かれて妖怪になってしまったとはいえ、鞠が悪魔とは禁欲にもほどがあります。
「トラスカラ人の罪」エレーナ・ガーロ(La culpa de los tlaxcaltecos,Elena Garro,1964)★★★★☆
――台所の戸を叩く音が聞こえて、ナチャは戸をそっと開けた。ラウラ夫人は焼け焦げと泥と血がこびりついた白いドレスを着たままだった。「若奥さま!……てっきり、もう亡くなったものと思い込んでいました」「亡くなったですって?」夫人は悲しげだった。「悪いのは、トラスカラ人だと思わない?」「はい、若奥さま」「わたしはあの連中と同じ裏切り者なの。ねえ、ナチャ、あの旅行でガソリンが切れたとき、お義母さまは旅行者の車で修理工を探しに行っちゃって、あたしは置いてきぼりにされたの。湖の前で目眩に襲われると、そのとたん、あの人の足音が聞こえたのよ」
メキシコ出身。これは解説を先に読んで歴史背景を理解してから読まないとわかりづらい作品でした。トラスカラとはスペインの侵略に屈して協力してアステカを滅ぼした中南米の国家の名前で、家族を殺されたアステカ人の妻ラウラが「時の裂け目のひとつから逃げ出して」現代で別の人生を送っていたところに、恐らくは戦死した元夫が現れて二人で元の世界に帰ってゆくという話です。妻が信頼できる料理人ナチャに語っているという形式もわかりづらさの理由の一つになっていました。山本周五郎「その木戸を通って」あたりを連想しますし、似た着想のSFも多分あるのでしょうが、アステカを材に採るのはやはりラテンアメリカならではだと思います。
「日蝕」アウグスト・モンテローソ(El eclipse,Augusto Monterroso,1959)★★★★☆
――道に迷ったバルトロメ・アラソラ師は覚悟を決めた。目を覚ますと先住民の一群に囲まれ、祭壇の前で生贄にされようとしていた。彼はその日皆既日蝕が起きることを思い出し、その知識を利用することにした。「私を殺したりすれば、空にある太陽を隠してしまうぞ」
グアテマラ出身。世界一短い小説「恐竜」の作者として有名です。先住民に対する先入観・偏見が、マヤという誰もが知っている常識によって軽やかに覆されるショート・ショートです。
「II 暴力的風土・自然/マチスモ・フェミニズム/犯罪・殺人」
「流れのままに」オラシオ・キロガ(A la deriva,Horacio Quiroga,1912)★★★☆☆
――男は毒蛇に嚙まれた。男はかがんで嚙まれた箇所の血を拭うと、自分の小屋めざして歩き続けた。脚の痛みはさらに増し、腫れて刺すような痛みが走った。それは傷に始まり、ふくらはぎの半ばまで達した。小屋にたどり着いた頃には暗紫色に変わり、早くも壊疽を思わす光沢を帯び始めた。死にたくはない。川岸に下りて行き、カヌーに乗った。流れに乗ってしまえば町まで五時間で着くはずだ。川の流れは速い。
ウルグアイ出身。本書収録作家のなかでも最古参、ラテンアメリカ文学ブーム以前の作家でした。蛇に咬まれてなすすべもなく町を目指すなか、最後は記憶が混乱して唐突に力尽きるという容赦のない現実が描かれていました。
「決闘」マリオ・バルガス=リョサ(El desafío,Mario Vargas Llosa,1958)★★★★☆
――俺たちがビールを飲んでいると、レオニダスが姿を見せた。「フストが今夜、やるんだとよ」。昼過ぎにフストとちんばがばったり出くわし、〈筏〉でやることになったそうだ。「あいつ、ちんばに殺られちまうぜ」「黙ってろ」。フストと合流し、〈筏〉に行くと、ちんばたちの姿が見えた。「なんでレオニダスを連れてきたんだ?」ちんばがかすれ声で言った。「連れてきてもらう必要なんかねえ。わしは自分の足できたんだ。それは口実で、本当はやりたくないんならそう言いな」「わかったよ、じいさん」。フストとちんばはナイフを確かめ合い、向かい合った。
ペルー出身。初めから終わりまで、いがみ合っている男二人が決闘するというだけの話です。周りの男たちも決闘者二人を尊重して見守り、協力し、たとえ実の息子が死んでも決闘を尊重し決闘をやり切った息子を誇るという、バトル漫画のような中二病的男らしさが横溢していました。この作品自体はフィクションとはいえ、当時のペルーの田舎には恐らく現実にこういう世界があるのでしょう。
「フォルベス先生の幸福な夏」ガブリエル・ガルシア=マルケス(El verano feliz de la señora Forbes,Gabriel García Márquez,1982)★★★☆☆
――家に戻ると首を扉のかまちに釘づけにされたウミヘビを見つけた。弟が悲鳴をあげて逃げ出したので、フォルベス先生に自制心の無さをとがめられた。彼女はぼくと弟の行いを重箱の隅をほじくるように点検する。父がドイツ人の女性家庭教師を雇ったことで、夏休みの宴は終わった。ところがまもなく、先生が自分に対しては他人に対するほど厳格でないことに気づいた。
コロンビア出身。ホームグラウンドであるコロンビアを離れて、イタリアを舞台にした作品です。厳しい指導を恨んで家庭教師を殺そうとする弟の、近視眼的な思い込みが、子どもらしいというよりも唐突すぎてついていけませんでした。唐突といえば結末も、鮮やかというよりも強引だと感じました。イタリアが舞台なのは愛や情熱による殺人というイメージによるものだと思うと、世界的文豪でもそうしたステレオタイプを書くのかと微笑ましくなりました。
「物語の情熱」アナ・リディア・ベガ(Pasión de Historia,Ana Lydia Vega,1987)★★☆☆☆
――そのころ私は、ちょっと前に起きた情熱的犯罪を題材に作品を書いているところだった。けれど日が経つにつれて、集中力はとぎれてしまう。そんなときにビルマから手紙を受け取り、フランス・ピレネーの小さな村で一緒に三週間過ごさないかと言われた。用意されていたのは快適な部屋で、洒落た書き物机まであった。「ここで何か生めなけりゃ、あんたはただの石女ってことよ」。やがてビルマが暴力をふるう夫のポールとうまくいっていないこと、義母はポールの味方をしていることなどがわかってきた。
プエルトリコ出身。書けないことの言い訳にあれこれ理屈をこねてゴシップに耽っているだけの語り手が痛々しい。編集部註にある「本書の原稿」というのが、作中作である「情熱的犯罪を題材にした作品」のことなのか、それを書こうとしている語り手の記録全体のことなのか、よくわかりません。
「III 都市・疎外感/性・恐怖の結末」
「醜い二人の夜」マリオ・ベネデッティ(La noche de los feos,Mario Benedetti,1968)★★★☆☆
――僕たちはとても醜い。彼女は頬骨が陥没していた。僕の口許にはぞっとするような火傷の痕がある。二人の眼差しは恨みに満ちている。知り合ったのは映画館の入口だった。僕たちは互いの醜悪さをまじまじと見つめ合った。映画が終わると出口で彼女を待ち、話しかけた。「あなたは世の中から追い出されたと感じているでしょう。バランスの取れた顔になりたいと思っている。僕だってそう思う。でも僕たちが何かを得る可能性だってあります」「たとえば?」「可能性は闇にあります」
ウルグアイ出身。解説によればタブーを破ろうとする時代の作品のようです。現実を覆い隠して理想で誤魔化そうとしてみたあとで現実を受け入れるという内容には普遍性がありました。
「快楽人形」サルバドル・ガルメンディア(Muñecas de placer,Salvador Garmendia,1966)★★☆☆☆
――僕が頻繁に勃起することと香のにおいの間には個人的な関係が存在する。『快楽人形』、それが今日、僕が選んだ一冊のタイトルだ。僕は広場のあたりをしばらくぶらつく。男たちが人ごみの中へ消え、続いて女性群が現れる。豊かな胸をした金髪娘の後を追うことにしたが、二ブロック先で台無しになる。喫茶店の入口で男が待っていた。
ベネズエラ出身。オナニーのネタを街で探して見つからなかった挙句にマリア像でオナニーした話だけの話にしか見えないのですが……。
「時間」アンドレス・オメロ・アタナシウ(Tiempo,Andrés Homero Atanasiú,1981)★★★★☆
――ハンスは窓のカーテン越しに外を見た。若い娘たちが海岸に向かって進んで行く。庭師を待っているのでなければ、その行列に仲間入りしたいところだった。すっかり伸びた植え込みを見ていると古い悲しみが甦った。クラーラとハンスは、幸福を期待できるかどうかも分からぬまま、酷しい孤独の中へ逃げこむことにしたのだった。彼らがなかなか来ない庭師を待っていたのは九月のことだ。
アルゼンチン出身。時間、それも人生の時間をテーマにしたオムニバス作品です。一話目の「庭師」は姿を見せない庭師を待ち続ける孤独な夫婦の話かと思いきや、なるほどそういう作風でしたか。庭師の正体からの連想か、ブラッドベリの初期の短篇を思い出しました。
「IV 夢・妄想・語り/SF・幻想」
「目をつぶって」レイナルド・アレナス(Con los ojos cerrados,Reinaldo Arenas,1972)★★☆☆☆
――あなたには全部話すよ。ぼくはまだ八歳だから学校に通っている。それが悲劇のもとなんだ。学校がすごく遠いので、いつもなら学校まで走って行く。でも昨日はちがった。ゆっくり歩いていると、猫につまづいた。かわいそうに、車にひかれたんだ。橋の上で立ち止まって下を見ると、子供たちがドブネズミをいじめていた。
キューバ出身。たぶんこれは訳が悪い。子どもの一人称は難しい。
「リナーレス夫妻に会うまで」アルフレード・ブライス=エチェニケ(Antes de la cita con los Linares,Alfredo Bryce Echenique,1974)★★★☆☆
――「ちがうんです、精神科医の先生、ぼくは変な夢ばかり見ると言ってるんです」「悪夢だな」「悪夢じゃないんです、精神科医の先生、むしろ滑稽なんですよ」「セバスティアン、わたしを精神科医の先生と呼ばないでくれ、セニョール・ミスターと呼ぶようなものだ。先生でいい」「分かりました、精神科医の先生、叔母さんがジョギングパンツをはいていたり、お祖母ちゃんがローラースケートを履いていたり、あんたがうんちをして……」
ペルー出身。夢というか妄想というか変なことを語り尽くす困った患者さんでした。
「水の底で」アドルフォ・ビオイ=カサーレス(Bajo el agua,Adolfo Bioy Casares,1991)★★☆☆☆
――肝炎が治った僕は、きれいな空気を吸うよう医者から勧められた。散歩していると、医者の家の桟橋に下りる階段に、えらく美人の女性が腰を下ろしていた。医者の姪のフローラだった。フローラには二十歳以上の上の恋人がいるということだったが、出会った僕たちは恋に落ち愛し合った。「湖に近づきすぎちゃだめよ」とフローラは言った。
アルゼンチン出身。療養先で遭遇した恋と三角関係の話かと思っていると、何をどう間違ったのか、科学者の若返り実験で鮭の内分泌腺を移植された六十歳の男が半魚人になってしまうというB級怪獣小説になってしまいました。
[amazon で見る]